 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/250 sec, ISO200)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/250 sec, ISO200)
※購入後1年数か月経ったため内容更新しました。
2月に思い立って「LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH.」を購入したのですが、これがなかなか自分の撮影観に影響を与えるような趣深いレンズだったので紙幅を割いてご紹介したいと思います。実は既にマレーシア日報でちょいちょい登場しているレンズです(^ω^)
なお、普段センサーサイズなどについて語ることはないのですが、今回は訳あってというか血迷ってというか、マイクロフォーサーズとボケ量の話なんかに触れちまったもんで、ちょっと長いですがご容赦下さいませm(_ _)m
購入理由:「明るい標準ズーム」では足りなくなった
こちら、筆者が所有するパナソニック製LEICAレンズ(所謂パナライカ)としては標準大口径ズーム「LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.」に続いて二本目になります。
明るい単焦点が欲しい、という漠然とした気持ちはずっとあったのですが、今の付けっ放しレンズパナライカ12-60mm F2.8-4や、フォーサーズ時代にはZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5 IIなど、そこそこいい写りをする大口径標準ズームをメインで使って来たため、敢えて単焦点に投資してもさほど投資対効果が無いのでは・・・などとついつい後回しになってしまっていました。
ん?後回しに「なってしまって」・・・??
いやいや、そんなもの後回しどころか永遠に買わなくたって全然問題ないはずなのですが(笑)
そんな中、最近直接的なきっかけが二点ほどありました。
一つは、年末に買い戻したフォーサーズの梅クラスの望遠ズーム、ZD 70-300mm F4-5.6で感じた、やっぱり安いレンズと良いレンズには目が節穴の筆者にも分かるような違いがあるかもな~と感じた事。(あ、あのレンズ、買った時と同じくらいの値段で売っちゃいました^^;)
もう一つは、先日naoggioさんと訪れた渋谷のスペイン料理屋の雰囲気が素晴らしく、魅力的な室内をもっとよく撮れる明るいレンズがあったらな〜と思った事。
さて、そうこうしているうちに購入後2ヶ月ほど経ちましたので(※本記事初回公開時点)、詳細なレビューと作例をご紹介したいと思います。
類似レンズとの仕様比較
ではパナライカ25mm F1.4がどのような位置づけにあるのか、同じマイクロフォーサーズの25mm(換算50mm)の標準単焦点レンズ群との主な仕様を比較してみます。
| LEICA DG SUMMILUX
25mm/F1.4 ASPH. |
M.ZUIKO DIGITAL ED
25mm F1.2 PRO |
LUMIX G
25mm/F1.7ASPH. |
M.ZUIKO DIGITAL
25mm F1.8 |
|
| 焦点距離 |
25mm | |||
| 開放F値 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 |
| 最大径×長さ | 63×54.5 mm | 70×87 mm | 60.8×52 mm | 57.8×42 mm |
| 重量 | 200g | 410g | 125g | 137g |
| フィルター径 | 46mm | 62mm | 46mm | 46mm |
| レンズ構成 | 7群9枚 | 14群19枚 | 7群8枚 | 7群9枚 |
| 最大撮影倍率
※()内は35㎜換算 |
0.11倍
(0.22) |
0.11倍
(0.22) |
0.14倍
(0.28) |
0.12倍
(0.24) |
| 最短撮影距離 | 0.3m | 0.3m | 0.25m | 0.25m |
| 実勢価格(2020/9現在) | 39,000円前後 | 140,000円前後 | 25,000円前後 | 35,000円前後 |
まずサイズ・重量については、パナ、オリ両社の廉価版のF1.7、F1.8のレンズを若干上回るものの、パナライカと同じ高画質扱いのオリンパスPROレンズの半分以下の重量と、非常に軽量コンパクトになっています。
それもそのはず、レンズ構成が7群9枚と、廉価版と同じような構成になっています。このカジュアルなレンズ構成でライカ画質をクリアしているのがこのレンズの凄まじいところです。
その代わり最短撮影距離や最大倍率は廉価版より劣っており、オリンパスのPROレンズと同等です。ここは画質とのトレードオフでしょう。
そして最後に再び驚きなのが価格。最安値だと3万円台で買えてしまうという、廉価版と完全に競合する価格設定!対するオリンパスのPROレンズは14万円とおよそ7倍以上。この両者の価格差ほどの画質の差を判別できる人間がいるのかいささか疑問です。
総じて、「ライカ画質」を認められた高画質レンズでありながら、非常に軽量コンパクトかつ安価で廉価版とも競合し得る二面性を持った(=非常にコスパの高い)レンズと言うユニークなポジショニングになっています。
特徴・外観・操作性など
サイズ感
まずは付けてみた感じから。OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II に付けた感じは至極コンパクトです。パンケーキとまでは行きませんが、結構クラシックな感じでこぢんまりとします。

操作性
・・・操作性といってもフォーカスリングがあるだけですが、適度にしっとりとしたトルクがあって扱いやすいです。
もっとも、AFも普通に速く使い勝手が良いのでプチマクロ的シーン以外ではMFの出番はさほど無さそうです。
あと、(構造上当たり前なのですが)最短撮影距離が30cmと、フルサイズの一般的な標準50mmレンズに比べてかなり寄れるのでテーブルフォトなどでも不自由なく使えます。(もっとも、同じM4/3のパナソニック25mmF1.7やオリンパス25mmF1.8は25cmとさらに寄れますが、十分でしょう)
絞り環がないのが残念という話は聞きますが、オリンパスボディではどっちにしても使えないので関係ありません^^;
外観
唯一残念なのは外観の質感・高級感。フォーカスリングはラバーだし、同じパナライカで金属鏡筒の12-60mm F2.8-4などに比べると質感は高くはありません。しかしその分下記の通りかなりお求めやすくなっております。
 Apple iPhone XS, (4.25mm, f/1.8, 1/20 sec, ISO640)
Apple iPhone XS, (4.25mm, f/1.8, 1/20 sec, ISO640)
価格
LEICA銘なので高いかと思いきや、本記事執筆時点で大体4万円前後と思いっきりお手軽!
発売当初でも6万円程度だった様なので、ライカ銘レンズとしては元々かなり手の届きやすい価格設定ですね。(ん?感覚麻痺してる?大丈夫??w)
このレンズの画角とF値の魅力:「25mm F1.4」はマイクロフォーサーズの苦手分野を克服させてくれる
ストリートスナップでハッとさせられた件
さて、このレンズでしか味わえない表現の醸し出し方が何となく分かってきた気がしたのは、マレーシアの屋台街で使い始めた頃でした。
大した写真ではありませんが、このレンズで初めて個人的にハッとさせられたのはこの一枚でした。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/80 sec, ISO200)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/80 sec, ISO200)
なんで?と思われるかも知れませんが、まず目を引いたのはトウモロコシを持っている女性の髪の質感です。一本一本を繊細に捉えており、まるで実物がそこにあるかのような再現力に驚きました。トウモロコシの実、一粒一粒の質感も伝わってきます。(ぜひ拡大してみて下さい)
それに、周囲はさほど大きくボケている訳では無いにも関わらず、この女性が浮き出しているような立体感を感じます。髪の毛などの合焦部分が非常に繊細でリアルな描写をしているのに対して周囲が非常に柔らかく階調豊かにボケているためかも知れません。
下の写真の女性のヒジャブの色合いと布目の質感も心地良いです。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO200)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO200)
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO250)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO250)
上の三枚はいずれも絞り開放で撮っていますが、共通しているのは、背景が狭く切り取られる事なく広範囲で写っており、それでいて被写体をそれ以外のものからくっきりと引き立たせるような自然なボケで浮き立てて見せてくれています。それはもしかしたら人間の目がものを捉えた時の感覚に近いのかも知れません。
50mmと25mmの境界線 | M4/3の標準画角はボケにくい
ところで、パナライカの描画などとはちょっと関係のないところで気になったことがありました。実はこのくらいのやや広めの画角かつ被写体との距離感で、被写体に立体感と臨場感を感じられるようなボケが得られる写真って、今まであまり撮れた事が無かった事に気付いたのです。そう、(マイクロ)フォーサーズ規格はこの手の表現が一番苦手なんじゃないかと思ってるんです。
もちろんマイクロフォーサーズ(M4/3)でも、単に「ボカしたい」という要望に応えるのは実に簡単です。寄る、あるいは望遠レンズを使い適切な距離関係を取れば、いとも簡単に大きなボケが得られます。
しかし、上のようなフルサイズ換算50mm程度の画角でかつストリートスナップ的な構図・距離感で自然なボケを得ようとするのは相当困難です。意識して工夫を凝らし、被写体と背景が絶妙な距離にハマらない限り、パンフォーカスで一見スマホ写真と変わらない平板な写真になってしまいがちです。
写真を趣味にされている方には釈迦に説法ですが、ボケ量を決める要素は以下の3つです。
- レンズの焦点距離 ←長いほどボケる
- レンズのF値 ←小さいほどボケる
- A(カメラと被写体との距離):B(被写体と背景との距離) ←Aに対してBが大きい(遠い)ほどボケる
センサーサイズはここには入ってきません。センサーサイズはボケ量ではなく「画角」に影響を与えます。
なので(すみません、ここ、だいぶ端折りましたw)、フルサイズに焦点距離50mmのレンズを付けた場合と同じボケ量をM4/3で得ようと思ったらどうすればいいかというと、(F値を変えないとすれば)単純に50mmレンズを使えばいいのです。
しかし、センサーサイズの違いによりこの場合フルサイズ換算100mm相当の画角になるため、背景もしくは被写体が狭く切り取られます。
なので結果的にM4/3ユーザーにとっては「焦点距離25mm」が、世間で言うところの「標準レンズ(フルサイズ換算50mm相当)」になるわけですが、問題はここからです。
この、50mmと25mm(フルサイズ換算とかは関係なく、純粋な焦点距離)の間辺りに、ストリートスナップ的な距離感の写真でボケを得られるか否かの境界線があるように思うんです。
つまり、例えばF2.8〜F3.5辺りで考えた時に、50mmと言う焦点距離はそれほど被写体に寄らなくても比較的容易にボケを得られます。(特にM4/3使いにとって50mmと言うのはもはや中望遠なので、「ボケが得られる」領域と言う感覚が強いと思います。)
一方同じ絞り値で25mmだと、結構寄らない限りボケないため、ストリートスナップ領域でボケを得るのは容易ではありません。(今度は銀塩カメラ時代の感覚の方が分かりやすいですが、25mmって当時の感覚だと完全に広角ですもんね。)
少し違う言い方をすると、25mm(換算50mm)よりも望遠方面(例えば45mm(換算90mm)とか)ではM4/3であってもボケを得るのが容易になり(「ボケる、ボケない」というより「どっちのボケが大きいか」という世界)、逆に25mmよりも短い広角域ではそもそもボケは期待しないので、やはり25mm(換算50mm)辺りで最もセンサーサイズによる物理的制約を感じる事が多い気がするんです。
「標準画角でボケないM4/3」に希望を与えるLEICA DG SUMMILUX 50mm F1.4
話をまとめると、M4/3では、ストリートスナップ的に背景を広く入れるようなフルサイズ換算50mm程度の画角で、被写体とそれなりに距離を置く(寄らない)という条件においては、背景をボカすのが難しいと言うことです。
そうした中で、背景を広く活かしたストリートスナップ領域で適度なボケを楽しませてくれる数少ない解の1つが、このパナライカ25mm F1.4(あるいはオリンパスのM.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROという選択肢も)なのではないかと思います。
25mmの焦点距離でかつこのような画角・距離感で、F2.8ではこのようなボケは得られません。
一方明るければ良いのかというとそうでもなく、M4/3のラインナップには12mmや16mmにもF2以下の明るいレンズはありますが、それらは焦点距離が短すぎて寄らないとボケは得られませんし、逆に45mm前後だともはや中望遠なので狭い範囲を切り取る感覚になってしまい、少し違います。
そうした絶妙な画角とボケの雰囲気を後ほど作例でご覧頂ければと思います。
(後日追記)その後結局α7IIをサブ機として購入しました。マイクロフォーサーズとフルサイズのボケ量の違いについてはこちらの記事で詳しく比べています。
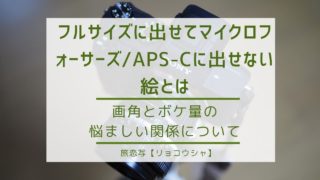
画質・撮れる絵の感じ:ライカらしさとは
さて、ここからは重要だけど曖昧なお話です。
LEICAらしい描写、などとよく言われますが、(本家の)ライカレンズを所有したことがないので正直言ってよく分かりません(笑)
とは言いつつ、プラシーボ効果かもしれませんが、個人的な感想・特徴としては、こんな印象です。
- ボケは確かにギスギスしておらず柔らかく滑らか
- 階調性が高く(飛躍せずなだらかで)、立体感を感じさせる
- ピント面は確かに繊細で、髪の毛や布目などを捉えると気持ちいい
「パラナイカ」という表現は半分揶揄も含んで使われることもありますが、個人的にはしっかりライカしてる、と感じます。
思えばこれらの特徴は、同じパナライカの「LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0」でも多かれ少なかれ当てはまる気がします。あのレンズにしてから、森などを写した際の枝や葉の描写は繊細でハッとさせられることがあります。
作例
さて、面倒くさい話はこれくらいにして(長くなりました(;´Д`))、パラライカ 25mm F1.4で撮った写真をもう少しご紹介していきますね。
蕩けるような柔らかなボケの写真から、上で長々と触れたように背景が大きくボケているわけではないのに何故かメイン被写体がレイヤー一枚分浮き出るような立体感が感じられる写真まで色々撮ってみたので、御覧下さい。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/250 sec, ISO200)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/250 sec, ISO200)
蕩けるようななだらかなボケで、近所のタリーズがお洒落なカフェのように見えます(^o^)
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/1250 sec, ISO200)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/1250 sec, ISO200)
紙ナプキンの繊維まできちんと見えますね。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/8000 sec, ISO125)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/8000 sec, ISO125)
ランプの中の文字まで見える繊細さと、浮遊感、空の色乗りが綺麗です。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/4.5, 1/60 sec, ISO500)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/4.5, 1/60 sec, ISO500)
こちらはマレーシアのビーフヌードル。具材の食感まで伝わってきそうです。
ここからは、そこまで背景が大ボケしていないのに立体感が感じられるくらいの距離感の作例たちです。
いずれもマレーシア、クアラルンプールのストリートスナップです。
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO500)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO500)
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO1000)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO1000)
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO500)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO500)
 OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO640)
OLYMPUS E-M1MarkII, LEICA DG SUMMILUX 25mm / F1.4 ASPH. (25mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO640)
人の視覚に近い画角で、自然に被写体を浮き上がらせる表現、フォーサーズやM4/3を使って来た筆者には新鮮で気持ちの良いものです。
それはもしかしたら、かつて銀塩の一眼レフカメラを使っていた頃の感覚を思い出したからかも知れません。
下の写真は2002年に訪れたラオスで、中古のペンタックスMZ-3という銀塩一眼レフにこれまた中古のMFの35-70mmF3.5-4.5を付けて撮ったものです。狭いトゥクトゥクの車内なので35mm域だと思いますが、広角端のF3.5でこの画角でここまでボケてくれるというのは今思うとすごいですね。
ということで・・・
余談:まさかのフルサイズへの興味・・・??
LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4を手にしたことで筆者の関心は思わぬ方向へ向かいました。上のような事をグルグル考えているうちに、
フルサイズ、ちょっと考えちゃおうかな・・・?
しかし、少なくとも完全移行は今のところ考えられません。なぜならフルサイズに乗り換えることによる機材の重量やサイズ、レンズの価格など多くの犠牲に対して、得られるメリットが小さすぎると感じたためです。
上で挙げたようなハーフポートレート×ストリートスナップ的な写真、海外だから沢山撮ったものの、普段はあまり撮らないんです。
それに、普段のスキーやキャンプなどでは広角から望遠までこなせる上にコンパクトで明るいLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm F2.8-4.0がとてもいい仕事をしてくれますし、同じようなスペック・写りのレンズをフルサイズで購入することなど(価格的&サイズ的に)到底考えられません。
で、たま〜にハーフポートレート×ストリートスナップ的な写真を撮りたくなった時は、それこそLEICA DG 25mm F1.4を取り出せば良いわけです。
なので、もしあるとしたら、中古のα7もしくはα7II辺りを手に入れ、撒き餌の50mm単焦点一本と手持ちのオールドレンズで遊ぶか・・・と言ったところですが、いかんせん資金が足りません^^;
ま、それはしばらく楽しい悩みのタネにする事にして・・・(・∀・)
まとめ:パナライカ25㎜ F1.4は繊細な描写と豊かなボケのハイコスパレンズ
結論としては、パナライカ25㎜ F1.4 ことLEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4は素晴らしく繊細な描写と、銀塩35mm時代を思い起こさせてくれるようなM4/3離れしたボケに大満足です^^
4万円前後で買える素晴らしい描写のLEICA、M4/3使いで良かったと改めて思わせてくれました。(オリの25mm F1.2 PROは高いですからね^^;)
リニューアル版製品も発売されています。違いは防塵防滴対応などで、基本的な操作性や画質は変わらないようです。







コメント
このレンズ、時々ハッとするような画を出すことがあり、大好きなレンズです。
ピントリングのゴムに埃が着くのがちょっとイマイチですね。
四角いフードをつけるとよりクラシカルな雰囲気になって、EM1に似合いますよね!
Nさん、こんばんは。
どうもそのようですね。
平凡な画角なので平均的にいい画を撮るのはなかなか難しいですが、たまにとてもいい写真を撮らせてくれそうな感じですね。
そうそう、ゴムってのはいただけません。
もう少し高価でもいいので金属にしてほしかった・・・
フード、かっこいいのですが嵩張るのでどっかいってしまいまいした(笑)
こんにちは
難しいことはわかりませんが
柔らかなボケ感と繊細な描写でいいですね。
明るい単焦点 私は50mmと24ミリですが
登場回数が少ないです^^;
匿名さん、コメントありがとうございます。
はい、ボケの感じとピント面の繊細さがとてもいい立体感を生み出してくれます。
単焦点、やはり登場回数は少なくなりがちですかね。
ズームは便利ですもんね・・・
僕も普段一本だけ持っていくときはズームです^^;
こんばんは。
マイクロフォーサーズのは通称小ズミって呼ぶんでしたっけ。フォーサーズの大ズミは500gオーバーでめっちゃデカいですが、まだ使っています。
今はちょっとでもいいレンズだと価格が跳ね上がるので、新品でも3万円台で買えるというのは魅力ありますね。写りも申し分なさそうですし。大ズミが壊れたらポチっといっちゃうかもしれません。
ボケに関しては、自分も同じように思っています。準広角から標準域のボケってマイクロフォーサーズでは表現し難いですよね。ボケ味に拘ったオリのF1.2PROはそういうところを意識してるのかなと思いますが、揃えるには価格が高くて手を出し辛いです。17mmだけは欲しいなぁと思ってますが・・・
フルサイズはマイクロフォーサーズと併用だと、価格の下がっているボディに明るい単焦点1~2本でも十分楽しめそうですね。
Hiro Cloverさん、こんばんは。
大ズミをお持ちですか。
大ズミくらいの大きさの方が大口径レンズっぽくて嫌いじゃないです。
しかし小ズミ、この小ささでF1.4ってのもすごいですね。
F1.2PROシリーズ、魅力的ですが、高いですよね・・・
単焦点に10万前後ってのはなかなか勇気がいります。
フルサイズミラーレス、常に頭のどこかにチラチラ居るんですよね〜(笑)
できれば手ぶれ補正が欲しいので、α7iiかiiiがお手軽な値段になってきたら、ポチってしまいそうです。